小学校高学年になると、自分の絵が思うように描けないなと感じたり、周りの友達の描く絵や、教科書の静物画の質感がリアルさに「なんか自分の描いた絵って、ちょっと違うんだよな・・・」「もしかして絵が苦手なのかも」って思う事、ありますよね。スキルアップ美術レッスン(1)では、そんな悩みを解決するために、筆や水の基本的な扱い方についてお話しして来ました。
実は、私も小学校時代、水彩絵の具で色の塗り方が上手くできなくて苦労した生徒の一人でした。中学では、どこをどう塗るか丁寧に考えることて、良い評価をもらうことができましたが、もし筆の詳しい使い方や色の混ぜ方などを、もっと早くに知っていたら・・・と今でも思います。
でも、絵を描くことはずっと好きでしたから、「もっと良く描けるようになりたい」と言う気持ちは人一倍強かったんです。大切なのは「美術って楽しい!」「好きだからもっと自分の気持ちを表現したい!」という純粋な気持ちを大切に繋げていくことだと私は思います。そして客観的に物を見る力は、絵の表現の幅を広げるための重要なステップなんです。
この「美術レッスン2」では、まさにそんな「もっと絵を上手に描きたい!」「なるほど!」って思う様な子さんのためのヒント、とっておきの混色の秘密や絵の構図を考えるプロのテクニックをこっそりお教えします!ちょっとしたコツを知るだけで、お子さんの絵の表現がグッとレベルアップしますよ!
スキルアップ美術レッスン2:色と構図で絵の魅力を引き出す秘密のコツ!
いよいよオリジナルの色作りです。このコツを身につけたらグッと他のお子さんtたちと差が付きますよ!
・プロの技!「秘密のオリジナル混色」
「秘密?」のオリジナル混色って、なんだかワクワクしませんか?
でも特別な色は必要ないありません。実は、みんなが持っている基本の3色で、驚くほど豊かな色彩が作れるんです。
・ステップ1:色の3原色♥♣♦
小さなお子さんでも知っている3色・・・それは色の3原色、赤、青、黄色。なぜ3原色と言うのか?それはどんな色を混色しても作れない色だから。でも、この3色があれば、まるで魔法の様に、たくさんの色が作れますよ!
りんごの赤やレモンの黄色、空の青だけじゃなく、草や葉の色やブドウの色だって作れるんです。
では、この3色を混ぜたら何色になるでしょうか?
ネットでは黒に近い色と出ていますが、私の経験では、混ぜる色の量によって様々な表情を見せる「茶色」になると思います。
黄色が多ければ黄土色、青が多ければ焦げ茶色、赤が多ければ赤茶色です。
混ぜる色の分量によって無限のバリエーションが生まれるんです。お子さんは一気に筆でワーっと混ぜてしまいますが、ゆっくりと混ぜながら少しずつ色の変化を見て、自分の欲しい色を見つける様にすると良いでしょう。
絵の具セットの箱には、あらかじめ茶色、緑など用意されていますね。 幼児の段階では、まず絵の具に慣れることからなので、そのまま使っても構いませんが、お子さんの興味が出て来たら、実物の葉っぱと絵の具セットの緑を比べて見せて、同じ色かな?と問いかけてみましょう。自然の緑色は、青と黄色の混色で作れますよ。
 ヨハネス・イッテン「色彩論」美術出版社
ヨハネス・イッテン「色彩論」美術出版社
青と黄色で緑、青と赤で紫、赤と黄色で色オレンジ色。さらにできた色どうしを混ぜると、もっとたくさんの色が生まれます。
子どもたちにとって混色で色の変化はまさに魔法のようです。
全部混ぜたらどうなるの?どこに塗ろうかな?より、パレットの上で絵の具を混ぜる実験に集中してしまうかも知れませんね。でもそれも大切な経験です。色の実験としてできた色を一つずつ紙に塗っていくと世界でたった一つのオリジナルカラーチャートができて楽しい記録になりますよ。
・ステップ2:秘密の黒って?♠(混色で美しい黒と灰色)
さて、灰色を作るためにはどうしたら良いのでしょう?ほとんどの方は「黒と白!」とお答えになるのではないでしょうか?子どもたちもきっとそう答えます。いえ、いえ、でもね、もっと美しい黒ができるんです!
中学生になったら美術の時間に習うと思いますが「無彩色」と「有彩色」という色の分類があります。黒や灰色は無彩色ですね。でも彩りのある絵には黒も有彩色で作ると、さらに一層、深みのある色彩になるんです。
では、どうやって黒を作るのでしょう?
それは緑と赤を混ぜるんです。⇑上の色環図を見て下さい。赤と緑は、まるで真正面で話をしているみたいに向かい合っていますね。実はこのように向かい合った色同士を混ぜると灰色になるんです。
灰色は黒と白だけじゃないんですね。ただし、黒の場合は暗い緑(ビリジアン)と暗い赤(クリムソンレーキ)を使うとよいですが、通常は絵の具セットに入ってる赤で十分に間に合うはずです。緑が多いと青みがかった黒、赤が多いと紫がかった黒、これに白を混ぜると美しい灰色が生まれます!
以前、カルチャーの講座に見えた年長さんのお母様に「絵の具は何色あれば良いですか?」と聞かれて「色の3原色、赤、青、黄色に白とビリジアン(深緑)、この5色があれば大丈夫です」とお答えしていました。始めは「Ο色ってどうやって作るの?」と聞いてたお子さんも「わぁ〜水色になった!オレンジ、ピンクになった!」と歓声を上げていました。
・ステップ3:画用紙は舞台!主役を引き立てるプロの技

 幼児は形態感より感じたままを表します。
幼児は形態感より感じたままを表します。
机に並んだ色々な形、外へ出かけて描く写生会の絵。「うわー!なんだかたくさんある。何をどこから、どう描いたら良いのかな?」と迷ってしまうことがありますよね。
・絵の中でまず主役、脇役を決める(これはお芝居を作るのと同じです。例えば「桃太郎」で主役の桃太郎よりも、脇役の猿や雉の方が大きく良く目立っていたら、何だか変ですよね)まず、「今日の主役はこれ!」と、一番描きたいものを決める事で、周りの色や描き方も自然と決まって来ます。
・主役を目立たせるための配色を工夫する。
どんな色の組み合わせが一番目を引くのでしょうか?目立つのか?答えは上の色環図にあります。向かい合った色同士。これを「補色」と言いますが、もっともお互いを引き立て合いパッと目をひく目立つ組み合わせといわれています。
他にも色の明るさ「明暗」の差も大切ですね。例えば、白と黒の様に、明るい色と暗い色を隣同士に置くと、その境目がはっきりして、見た人の目が自然とそこへ引き寄せられます。
最近、子どもの施設で展示されてる風景画を見ました。左端に家の屋根の影で暗くなった軒下が真っ黒に塗られていました。軒下が、この絵の主役ではないはずです。とても残念でした。
主役が決まったら、画面の一番良い場所に入れてあげましょう!主役が端っこに小さく描かれていたら、折角の魅力も半減してしまいます。だいたい真ん中あたり、ど真ん中よりも少しだけ左右どちらかに1〜2cmずらすとバランスが良くなり、主役がグッと引き立ちますよ。
さぁ、次は脇役です。どこに脇役が登場すれば良いのかな?すぐ描き始めないで、まずは場所を決めることが大切です。指で、この辺かな?って画用紙の上を指し示しながら考えてみましょう。
人物や動物を描く場合、脇役がきちんと並んでいる必要はありません。むしろ手前に上半身だけ見せていたり、画面からはみ出ていたりする方が、絵に動きや奥行きが感じられて、面白くなりますよ。
静物画など机の上に色々な物が乗っている絵を描く場合は、自分の位置(目線)が大切です。自分から見て、一番左にあるのは何かな?右側にあるものは?
そして、物同士の背比べをしてみましょう。一番、背が高いのは?低いものは何?手前にある物や遠くに置いてあるもの、形の後ろに隠れて半分しか見えない物もあるかもしれません。横幅にも注目して下さいね。
例えば、「レモンと瓶の横幅は同じくらいだけど、瓶は一番、背が高いな。」と言うふうに注意して良く見ていくと、だんだんと形がつかめてきます。物を良く観察する事で、これまで気づかなかった発見があるかも知れませんね。
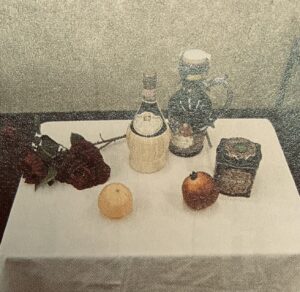
・プロの技!道具も大切にする後片付け術
絵の具や筆に使い慣れてくると後片付けが面倒に感じるお子さんもいるかもしれません。
でも、道具の手入れは本当に大切なんです。あのイチロー選手も毎日、自分のバットやグローブを大切に手入れをしていた話は有名ですよね。パレットや筆も同じです。パレットは絵の具がほとんど残っていなければ、その日、使った筆で水洗いしましょう。筆も、たまには石鹸で根元から丁寧に洗わないと絵の具が溜まってしまい、それが溶け出して描く色を濁らせる原因になってしまいます。
筆は手のひらに石鹸をつけ、筆の穂先優しくをグルグルと回して泡立ててみましょう。泡だったら、筆の根元を親指と人差し指で挟んで、絞るようにしごいてみて下さい。もし石鹸の泡の色が変わって絵の具の残りカスが出てきたら、それが「汚れていた証拠」です。
以前、小学生の女の子に道具の手入れの大切さの話をしたところ、次からは「ねぇ、先生!見て!この筆、綺麗?お風呂に一緒に入ってリンスもしたよ!」と毎回、嬉しそうに見せてくれる様になりました。

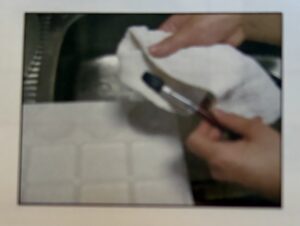
道具を大切にすることは、絵をより楽しむための大切なステップなんですね。
*スキルアップ「プロの技!(2)」まとめ・・・
・色の3原色について役立つ知識
・自分だけのオリジナル混色で差をつけよう!
・絵の中の主役と脇役(何をどこに、どんな大きさで描くかが大切)
・主役を目立たせるコツは?
・大切な道具の手入れもプロの技



コメント